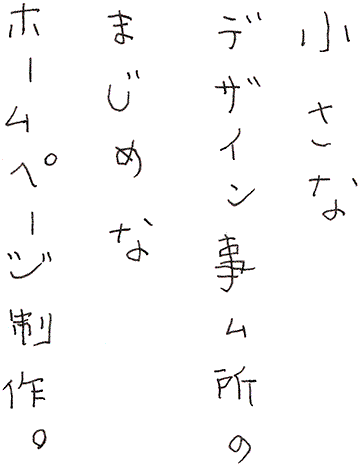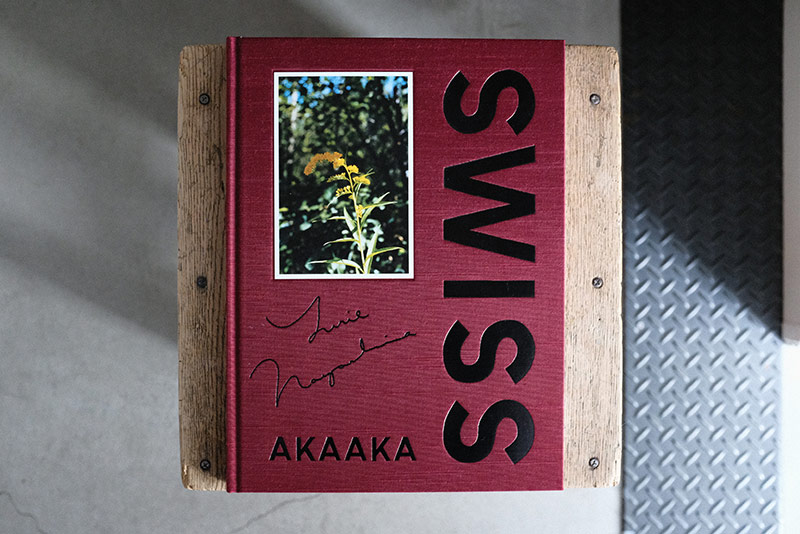「魔の山」の次は何を読もうか迷いましたが、世界10大小説の中から「白鯨」に決めました。上下巻あわせて1000ページ。魔の山の1500ページに比べたら3分の2だけど、それでもかなりの分厚さです。読み終えるまで何か月かかるかな。それにしても魔の山はなぜ10大小説に入っていないんだろう?絶対入るべきやろ。ぼくがこれまで読んだ小説で一番凄いと思ったのは・・・いや、一番とか決められないけど、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」「悪霊」はいずれも読み終えた後、しばらくその世界から抜けられませんでした。「悪霊」はすごかった。読んでいて面白いなーと感じたのは「カラマーゾフの兄弟」が一番かもしれません。サン・テグジュペリの「人間の土地」も感動しました。でも小説じゃないからあれか。もちろん「魔の山」もベスト10に入ります。短篇だったらマンスフィールドの「園遊会」、サン・テグジュペリの「夜間飛行」も良いなあ。とにかく次は「白鯨」を読みます。